![]()
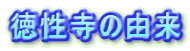
当寺は親鸞聖人を宗祖と仰ぐ浄土真宗本願寺派に所属する寺です。
当寺の「御旧跡略縁起」「天保由緒書」によりますと、往古は天台宗豊原三千坊の一宇で西潟の西芳寺と称したとあります。本願寺の八代目、蓮如上人が加賀越前の境の吉崎に滞在中、文明五年(1473)加賀の山中温泉ご入湯の途中、当菅谷村に立ち寄られました。上人は越前藤島の超勝寺より、国境の大内峠を越えて、当寺の前の石に腰を掛け休憩されました。
当寺の住持と問答になり、上人は椿の杖を地面に刺し、私が説く弥陀の本願の教えは、善人も悪人もすべての者が必ず救われるという教えであり、これがまことならば、この杖の下から清水が湧き出るだろうといわれ、杖を抜くと清水が湧き出たと伝えています。その清水を蓮如清水・椿清水と名づけ今に伝えています。住持は直ちに上人に帰依し、上人から法名教願を授けられました。
上人はこの折、一粒の梅の実を撒いて次の歌を添えられました。
撒きおきし一粒種に八房の
実のらば弥陀の誓いとぞしれ
実りにくい八房の梅、すなわち救われることの難しい煩悩具足の人間が救われることがあるならば、弥陀のご本願しかないとの仰せであろうと思われます。
境内の旧跡・・・・・○椿清水 ○八房の梅 ○お腰掛けの石
本堂の宝物・・・・・○蓮如上人御影 ○楷書六字名号 ○三方正面阿弥陀如来絵像
○椿の御杖 ○水晶の念珠 等
また、西潟の西芳寺について、寿永二年木曽義仲が上洛の軍を進め、篠原において合戦となり、その折平家の武将であった斎藤実盛の臣、須崎理左衛門が主君の菩提を弔うために、当菅谷の地に逃れ農夫に身を隠していたが、豊原寺に到り剃髪して徳性坊と称していたとの伝承もあります。
|
|
|||
| 和暦 | 西暦 | 事 項 | 参 考 |
| 文明3 | 1471 | 蓮如上人 吉崎来錫・御坊建立 | |
| 文明5 | 1473 | 蓮如上人山中温泉来錫当寺に立ち寄られる | |
| 阿弥陀如来・蓮如上人御影・六字名号頂戴 | |||
| 教願弟子となる | 開基教願 | ||
| 文明7 | 1475 | 蓮如上人吉崎退出 | |
| 明応9 | 1500 | 実如証判御文章 | 1500〜1525年間か |
| 文禄元 | 1592 | 顕如上人真影 | |
| 寛永14 | 1637 | 寺号木仏御免 | |
| 寛永17 | 1640 | 蓮如上人真影裏書き御免 | 良如上人御改裏書き |
| 康安2 | 1649 | 木仏寺号許可(願主教願) | 裏書き良如花押 |
| 貞享元 | 1684 | 五帖御文章 | 寂如御判 |
| 貞享5 | 1687 | 鉄砲改め | 教願 |
| 宝永2 | 1705 | 寺地拝領 | |
| 享保5 | 1720 | 親鸞聖人御絵伝 | 寂如上人裏書き |
| 明和元 | 1764 | 七高僧図・太子尊形 | 法如上人裏書き |
| 天明3 | 1783 | 本堂再建 | |
| 寛政7 | 1795 | 親鸞聖人真影 | 文如上人裏書き |
| 天保4 | 1833 | 鐘楼堂建立・梵鐘寄進 | |
| 天保6 | 1835 | 大門建立・天保由緒書き | |
| 嘉永2 | 1849 | 御領主立ち寄り | |
| 嘉永6 | 1853 | 本堂再建 | |
| 明治11 | 1878 | 明如上人御消息 | 菅谷惣同行中宛 |
| 昭和17 | 1942 | 梵鐘仏具等供出 | |
| 昭和48 | 1948 | 梵鐘再鋳 | |
| 昭和31 | 1956 | 土蔵再建 | |
| 昭和58 | 1983 | 本堂屋根改修・書院新築 | |
| 昭和59 | 1984 | 即如門主来錫 | |
| 平成10 | 1998 | 本堂雪囲い新築 | |
| 平成15 | 2003 | 帳場増築・法中玄関改築 | |
| 平成17 | 2005 | 蓮如上人銅像建立 | |